つむぎての里山❶「農福連携」と「自然循環型栽培」【Nagakute Times】
長久手東部里山エリアの一角に自然循環型の栽培の純粋さと奥深さに惹かれた岩瀬清佳さんら4人が立ち上げた「つむぎて(合同会社つむぎて)」の共同作業の要の場所であり、活動拠点があります。
岩瀬清佳さんはじめ4人の共同代表は、各々がまったく異なる分野で働いていたため、4人の体験と知見、そしてひらめきやアイデアが掛け合わされることになり、「つむぎて」のアウトプットは多様で厚みがあります
「つむぎて」は様々な事情で耕作されなくなった耕作放棄地や遊休農地を再生するために「農福連携」(農業+福祉)からはじまり、自然と関わり、自然と学びながら土地を<再生>してきています
その経過の中でこの里山の一隅の<景色>がものの見事に一変していきました。人の手がさまざまに添えられ、自然と分かち合って成り立つ里山のことを「つむぎて」の活動は教えてくれます
2025年の新年もまた自然への静かな祈りからはじまりました

「つむぎて」の圃場(ほじょう、農作物を栽培するための場所)への入り口(2025年1月8日撮影)
「里山」は、人の手が添えられてはじめて成り立つ自然環境




つむぎての圃場のすぐ奥手、江戸時代の頃よりひっそりとある溜池の杁ノ洞上池

杁ノ洞上池から引かれている水路
「つむぎて」の圃場を潤す貴重な水路。水のせせらぎと鳥の囀りが谷津の空間に絶えず木霊しています(2024年3月撮影)

「長久手東部大草の奥地にあるこの場所は、つむぎてのメンバーが幾つかの候補から探し出した場所でした。当初は車で奥まで入ることができなかったため長久手の施設の子供たちがはたして奥まで歩いていけるかなという懸念があったのですが、この地で始めてみることになったんです
でも現実、施設の子供たちにとっては歩く距離など大変な部分があって、土地は借りたまま当初の目的は果たせないままでした。その場所は今でも福祉施設の方が借りられています。ただその後続けるのが難しくなったため現在は私たちが管理をしています
この場所は「農地」なので作物を栽培しなくてはならないんです。ところが作物を植えてもイノシシやカラスにやられてしまい試行錯誤が続きました。獣害対策をしてもそれを超えて荒らされてしまうんです。そして次の一手をまた考えます」(岩瀬清佳 談)



「トンボが飛んできて、鳥がやってきて自然の循環を感じました。なんて素敵なところなんだろう。それにホタルもいたんです」
「つむぎて」の始まりは7年前、圃場脇に「道」をつくることからはじまったといいます。次にもともとやっていた畑から椎茸の原木を一本一本を肩に抱えながら150本運び込んだといいます
(2025年3月10日撮影)

少し奥に入った所も「つむぎて」が土地の手当てをしている。ここにも跡継ぎがなくなってしまったりオーナーがご高齢になりいわゆる耕作放棄地や遊休農地になってしまった所がある。ショベルカーや田植え機が入ってこれないので農地の再生は人力で行うしかない



つむぎての共同代表の一人、猟師の加藤康次さん
農地を荒らしまわってしまう野生のイノシシの捕獲やカラス対策などつむぎての圃場だけでなく、この谷津の里山持続可能性は彼の手にかかっている

「つむぎて」では指定現場圃場の植生調査、雑草講座の依頼、相談をおこなっている
専門の知見を持ったつむぎての共同設立者である前田純さん :(京都大学農学研究科農学専攻雑草学研究室出身 雑草料理研究家)が、食べられる雑草のことや雑草の可能性を日々探求している
『美味しい雑草図鑑』(前田純 著 扶桑社)2025年3月27日発売
前田純氏の知見をもとにこの場所で採取されるある雑草をもとに優れた化粧品が開発された(正式な化粧品の原料であるという許可を米国で取得し安全性試験済み)。詳細は後日にレポート予定

(2025年1月5日撮影)

*Google Mapの終点は、大草の永見寺になっています。永見寺の手前、大草公会堂の左側の道を奥に入っていき、永見寺を左手に見て里山の奥へと入っていきます。クルマは途中の杁ノ洞下池まで一応入れますが、地元の方の住居がすぐ近くにありますので長居は避けてください。そこから奥へ続く小径は徒歩になります






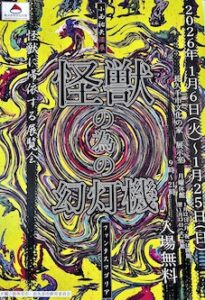









Hello! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to mention keep up the great job!
My wife and i were really fulfilled Michael could round up his basic research through the precious recommendations he had when using the site. It’s not at all simplistic to just find yourself handing out solutions which usually some other people have been making money from. And now we take into account we now have the blog owner to thank because of that. The entire illustrations you’ve made, the simple site menu, the relationships you assist to engender – it is everything astounding, and it is facilitating our son in addition to our family imagine that the theme is brilliant, which is certainly exceedingly important. Thank you for the whole lot!
As the admin of this website is working, no
uncertainty very shortly it will be famous,
due to its feature contents.
demais este conteúdo. Gostei bastante. Aproveitem e vejam este conteúdo. informações, novidades e muito mais. Não deixem de acessar para aprender mais. Obrigado a todos e até mais. 🙂
demais este conteúdo. Gostei muito. Aproveitem e vejam este site. informações, novidades e muito mais. Não deixem de acessar para descobrir mais. Obrigado a todos e até a próxima. 🙂
amei este site. Pra saber mais detalhes acesse nosso site e descubra mais. Todas as informações contidas são informações relevantes e exclusivas. Tudo que você precisa saber está está lá.
I needed to write you this little remark in order to thank you very much yet again for those pleasant tactics you’ve discussed on this website. It was extremely generous with you to grant publicly just what numerous people would have supplied for an e-book in order to make some cash for their own end, precisely given that you could possibly have done it in case you desired. The good ideas in addition worked as a good way to be sure that other individuals have similar passion really like my own to grasp somewhat more in respect of this matter. I believe there are some more fun instances in the future for individuals who scan through your website.
I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.
Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just spectacular and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.
Great post. I was checking continuously this weblog and I’m impressed! Extremely helpful info specially the closing phase 🙂 I maintain such information much. I was looking for this certain information for a long time. Thanks and best of luck.
Real instructive and superb complex body part of written content, now that’s user pleasant (:.
great post.Never knew this, thankyou for letting me know.
As a Newbie, I am permanently exploring online for articles that can benefit me. Thank you
Very interesting details you have noted, regards for putting up.
You really make it seem really easy together with your presentation but I to find this topic to be actually something that I feel I’d by no means understand. It seems too complicated and very wide for me. I’m taking a look forward for your next post, I will attempt to get the hold of it!
Wohh precisely what I was searching for, thankyou for putting up.
What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.
Somebody essentially assist to make significantly posts I’d state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual publish amazing. Magnificent activity!
This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen
I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂
Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips for rookie blog writers? I’d genuinely appreciate it.
whoah this weblog is fantastic i love studying your posts. Keep up the good paintings! You realize, many people are searching around for this info, you can aid them greatly.
hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..