草と竹でつくった里山のモニュメント「草の家」/つむぎての里山❷【Nagakute Times】
長久手東部里山エリアの一角に自然循環型の栽培の純粋さと奥深さに惹かれた岩瀬清佳さんら4人が立ち上げた「つむぎて(合同会社つむぎて)」の共同作業の要の場所であり、活動拠点があります。
その経過の中でこの里山の一隅の<景色>がものの見事に一変していきました。人の手がさまざまに添えられ、自然と分かち合って成り立つ里山のことを「つむぎて」の活動は教えてくれます
今回は、つむぎての活動が一味違うことを象徴的にあらわしているかのような草と竹でつくられたまるで縄文時代の小さな住まいのような「草の家」を中心にレポートします


2025年1月8日撮影

「つむぎて」のモニュメント:「草の家」のこと
「何かモニュメントを作ろうということになって、刈り込んだ草と竹を集めて組んでみたんです。
それが私たちが「草の家」と呼んでいるものになりました」(岩瀬清佳 談)
台風が来てもこの「草の家」だけは飛ばされないんです

「竹で組んで草を被せて建てかけているだけなんですけど、不思議なことに台風が来ても風で飛んでいかないんです。つくってから年数が経ってきたのでスカスカになるのでまたススキなどを用いて葺き替えしてます。
つむぎてってこの地で何をしている人たちなんだろうと興味を持ってもらって、まずは知ってもらうきっかけになればいいかなと思って皆でつくったんです」(岩瀬清佳 談)

風にゆれるススキの穂。まるでこの里山の自然神を迎えいれ、里山に季節の到来とともにまた巡ってくるものを受け入れ祈りを捧げているかのようです

2025年1月8日撮影
「草の家」には無駄が一つも無いんです!

「楠の木を燃やして貝を焼いています。そうするとその煙で燻(いぶ)されて草や竹が長持ちするんです。
楠の木は樟脳(しょうのう)の元になって虫除けになるんです。煙が立ち込めると虫たちがさっと外に出てくれるんです。腐らないんです。その火で貝を焼いているんですね。
私は藍染(あいぞめ)の藍を栽培しているのですが、藍染の染液にもいいんです。燃え尽きた後の楠の木の灰も藍染の活性剤になるんです。
つまりこの「草の家」じたい無駄が一つもないんです。これもまた自然循環型になっているんです」(岩瀬清佳 談)


「つむぎて」のサイトはこちらへ / 岩瀬清佳さん 3月




*Google Mapの終点は、大草の永見寺になっています。永見寺の手前、大草公会堂の左側の道を奥に入っていき、永見寺を左手に見て里山の奥へと入っていきます。クルマは途中の杁ノ洞下池まで一応入れますが、地元の方の住居がすぐ近くにありますので長居は避けてください。そこから奥へ続く小径は徒歩になります






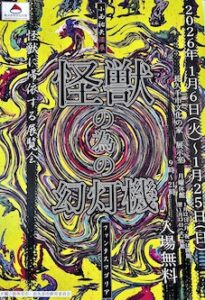









Just wanna remark that you have a very decent website , I like the style it actually stands out.
Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!
I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!
Some truly interesting details you have written.Aided me a lot, just what I was looking for : D.
Im now not positive where you are getting your info, however good topic. I must spend some time learning more or figuring out more. Thanks for great info I used to be in search of this info for my mission.
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade strategies with other folks, be sure to shoot me an email if interested.
I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.
Este site é realmente fabuloso. Sempre que consigo acessar eu encontro coisas boas Você também vai querer acessar o nosso site e descobrir mais detalhes! Conteúdo exclusivo. Venha saber mais agora! 🙂
There are actually a lot of particulars like that to take into consideration. That may be a nice level to convey up. I provide the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you carry up the place an important thing will probably be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, however I am positive that your job is clearly identified as a good game. Both boys and girls feel the influence of only a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.
You are a very bright person!
My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be exactly I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web log!
Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!
Real clear site, regards for this post.
I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?
Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol
I’m impressed, I need to say. Actually rarely do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you will have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the issue is one thing that not enough people are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my search for something regarding this.
This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.
I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?
You made some nice points there. I did a search on the topic and found most individuals will agree with your website.
Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Cheers!
Some really interesting info , well written and broadly speaking user friendly.
I’ll immediately clutch your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognise in order that I may subscribe. Thanks.