愛知用水に難関だった「橋」が架かる/瀬戸大府東海線レポート【Nagakute Times】
長久手里山エリアを南北に走る県道57号「瀬戸大府東海線」の道路工事の最新レポートです。今回は愛知用水に難関だった橋がかかった様子と、丘陵を貫通する造道の様子のレポートとなります
愛知用水への架橋がおよそ完了したことで、「瀬戸大府東海線」の大草交差点までの造道が着実に進んでいるのがみてとれます
「5ヵ年加速化対策」も残り1/3くらいに突入しているのではと思います
(画像は2月上旬撮影)



長久手市の北方から南方へと流れる愛知用水への架橋は、今回の道路工事で最も困難なものです
道路上の交通量は極めて多く、大型車、ダンプカーが利用する頻度も高いため大地震の振動や極限の荷重に対する構造的強度が必要になります
橋の下を流れる愛知用水が毀損されるとその下流域の広域の水管理システムに甚大な影響が出るため、半年以上かけ慎重な架橋工事が行われていました。


後ろに見えるのは岩作御嶽山。道路は岩作御嶽山の東側の丘陵部分を南北に貫きます



写真の奥が瀬戸市方面
瀬戸大府東海線(長久手工区)の「5か年加速化対策」は、予想されている災害時の物資・人材受け入れの起点となる東名高速道路・名古屋ICと長久手ICへのアクセス性向上を図るため。
また、混雑する長久手市中心部を迂回したネットワークを形成し「緊急輸送道路網」の機能強化を促進するため、及び地域防災力の向上に貢献するためのバイパス整備事業になっている。

この道路が南北のエリアをつなぐバイパス道路ともなり、長久手市内の道路の混雑緩和にもつながることに
道路の強靭化は災害時の移動や物資運搬にも必須となります





コメントを残す
関連記事
人気記事









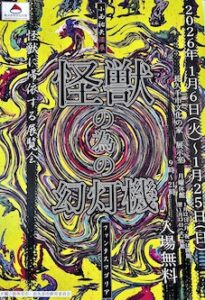









Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks
fabuloso este conteúdo. Gostei bastante. Aproveitem e vejam este site. informações, novidades e muito mais. Não deixem de acessar para saber mais. Obrigado a todos e até mais. 🙂
me encantei com este site. Pra saber mais detalhes acesse nosso site e descubra mais. Todas as informações contidas são conteúdos relevantes e exclusivos. Tudo que você precisa saber está ta lá.
I have recently started a site, the information you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.
Good write-up, I?¦m normal visitor of one?¦s website, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.
I?¦m no longer positive the place you’re getting your info, however great topic. I needs to spend a while studying more or working out more. Thank you for great information I used to be looking for this information for my mission.
excellent issues altogether, you simply received a new reader. What could you suggest in regards to your post that you simply made some days in the past? Any sure?
I haven?¦t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂
With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any techniques to help reduce content from being stolen? I’d certainly appreciate it.
Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.
Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!
You need to participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I’ll recommend this web site!
Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!
Hi there very nice blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I’m happy to find so many helpful information here within the put up, we need work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.
Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!
I conceive this internet site holds some really excellent info for everyone : D.
I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!