長久手でも目撃されだした国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」のこと。本当? /県下の「里山」機能の弱体も原因の一つか【Nagakute Times】

画像:Wikipediaより
ニホンカモシカは、ウシ科カモシカ属に分類され、シカよりもヤギや牛に近いとのこと
雌雄とも枝分かれのない2本の小さな角があります
日本固有種で、京都以東の本州と四国、九州の一部にかけ広く分布。鈴鹿山脈や紀伊半島にも多い
1934年に国の天然記念物に、1955年に国の特別天然記念物に指定された
そのため無許可で触ったり、捕獲したり、飼育することは法律で禁止されています
性格は温厚で、人に向かって攻撃的になることはほぼないが、無闇に近づいたり脅かすと角で人間を突いた事例はままあるそうです
2025年5月30日藤が丘すぐ西方にある明が丘公園、そして6月2日にかけて名古屋市名東区で目撃されていたニホンカモシカ
場所は、一社の北方、名東区図書館裏の廻間(はざま)公園内
「カモシカ保護管理マニュアル」文化庁文化財第二課
長久手市内に1ヶ月近くいたと推測されるニホンカモシカ
おそらくその後、→守山区東部→名東区へ移動か
国の天然記念物ニホンカモシカの目撃情報は2025年5月20日岩作の丸根付近とのこと→長久手市ホームページ
2025年4月20日には、AEON長久手の南西方向の山越地区で目撃されてます
山越地区から丸根付近での目撃はちょうど1ヶ月。その間、ニホンモシカはこの辺りをうろうろしてたのでしょう。途中、ちょうどドングリや木の葉が豊富な古戦場公園が広がっているので食料を補給していたのかもしれません
長久手市への侵入経路としては、瀬戸南部の尾張東部丘陵(以前ですが海上の森やモリコロパーク近辺でも目撃例あり)か、豊田西部の丘陵エリアから三ヶ峯地区経由で長久手中央部にまで侵入してきたと考えられます
ナオさんTVういんどなお Youtube動画より 2021年 撮影場所は愛知県下ではありません
愛知県のニホンカモシカの分布は、1970代から奥三河から西部へ、
尾張東エリアにじょじょに拡大
落葉広葉樹林に沿って西へ移動
愛知県のニホンカモシカの生息地は、1970年代前半までは奥三河一帯(豊根町、設楽町、東栄町)に限られていたといいます。その後、1980年代、90年代、2000年代へとすすむにつれ生息地域が拡大してきたことが調査で判明しているとのこと
2000〜2015年の目撃市町村:豊根町、設楽町、東栄町、豊田市、岡崎市、豊橋市、豊川市、新城市、瀬戸市、名古屋市(守山区)、長久手市、日進市
その後、小牧市、犬山市、春日井市、尾張旭市、東郷町でも目撃例が出てきたとのこと。そして今回の名古屋市名東区での目撃である
やはり生息地域は、西へ、西へと拡大しているといえます
植生の分布との関連で、愛知県北西部は落葉広葉樹林の二次林(雑木林)の西端にあたるとのことで、それに沿ってニホンカモシカの生息地域が拡大したようです
豊田市域ではすでにほぼ全域が生息地域に
2011年〜2019年の間にニホンカモシカとの交通事故は66件にのぼってるそうです
全国的には個体数は減少気味とのとこですが、豊田市では増えているとのこと
「豊田市域におけるニホンカモシカの死亡個体の発生状況とその傾向」(2021年 豊田市資料)



長久手東部里山の風景
ニホンカモシカの主食、食べ物 : 草食性です
ニホンカモシカは草食性です
秋の落葉期には、栄養価が高い低木の落葉広葉樹の葉・果実・花・冬芽(枝先ごと)・小枝を食べたり、広葉草本(葉・花)を好むとのこと。針葉樹は好みません
2015年当時で愛知県下のニホンカモシカの頭数は、1874頭
2010年の調査では、1372頭だったとのことで年々頭数は増えているとのこと
また同じエリアに生息するニホンジカの頭数が増えたため移動してきている現象がみられる
(「<人と自然 報告> 愛知県北西部のニホンカモシカ (Capricornis crispus) の 分布拡大について 辻 大和」)参照


薪炭林が広がっていた中山間地帯と平地の緩衝帯だった「里山」が弱ってきたために起きている現象とも!?
<里山の雑木林>は、多年生の草木の成長を阻むコナラやアカマツ、クロマツ、ハンノキ、シラカバといった陽樹林を人間が手を加え続けることで歴史的に維持されてきた
薪炭林(しんたんりん)とは 薪(まき)や炭を生産するための二次林(供給源)のことで、人間の生活(農山村での暮らし)になくてはならないものでした
それこそ里山や丘陵地の人里の周りにあり続け、人間が手を加え維持されてきた「雑木林」のことでした
この薪炭林はクヌギ、ナラ、カシ類が代表的な樹種で、10~30年ごとに適当な間隔をとって伐採し「雑木林」を維持してきたとのこと
(毎年少しづつ順番に伐採することにより後は自然に<再生産>が繰り返されるサイクルができあがるとのことです

長久手東部にある平成こども塾の施設前に広がる間引かれ整えられた竹林
「雑木林」と「人」との共生関係は、「縄文時代中期」の「焼畑耕作」にまで遡るともいわれています
20世紀半ば、家庭に化石燃料が普及すると薪炭林が不要隣、雑木林は適宜な伐採もされなくなり放棄され、常緑樹が繁茂していきます
「雑木林」が放棄され出すと、シイ類、カシ類、クスノキ、タブノキ、ツバキ類といった常緑樹が生えだし自然植生になるのですが、これまでの明るい「林床」を生活の場にしてきた生物にとってはその変化は深刻な脅威になるとのことです

長久手東部大草 里山にて 「つむぎて」の耕作地
こんにちその広葉樹林が自然の「天然林」に分類されているとのことで、「自然に任せて成りたった林」ということで伐採への批判が出ることもあるそうです
広範囲に放置されつつある「里山」は、マツ枯れやナラ枯れ(カビの伝染病)にやられ、結果里山に生きる生物の構成が変わっていきます
愛知県下でのニホンカモシカの西進もそうした「雑木林」や「里山」の弱体化と変化から生じている現象と捉えられるようです





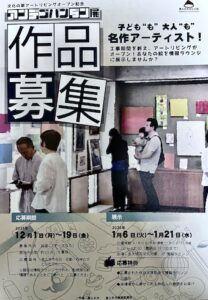





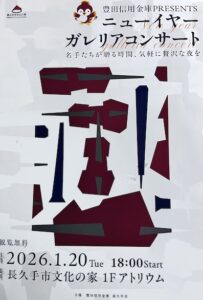
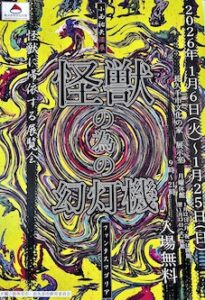


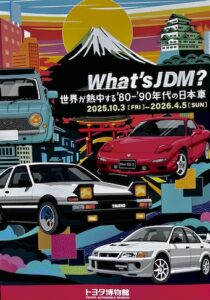







You made some decent points there. I looked on the internet for the topic and found most people will approve with your blog.